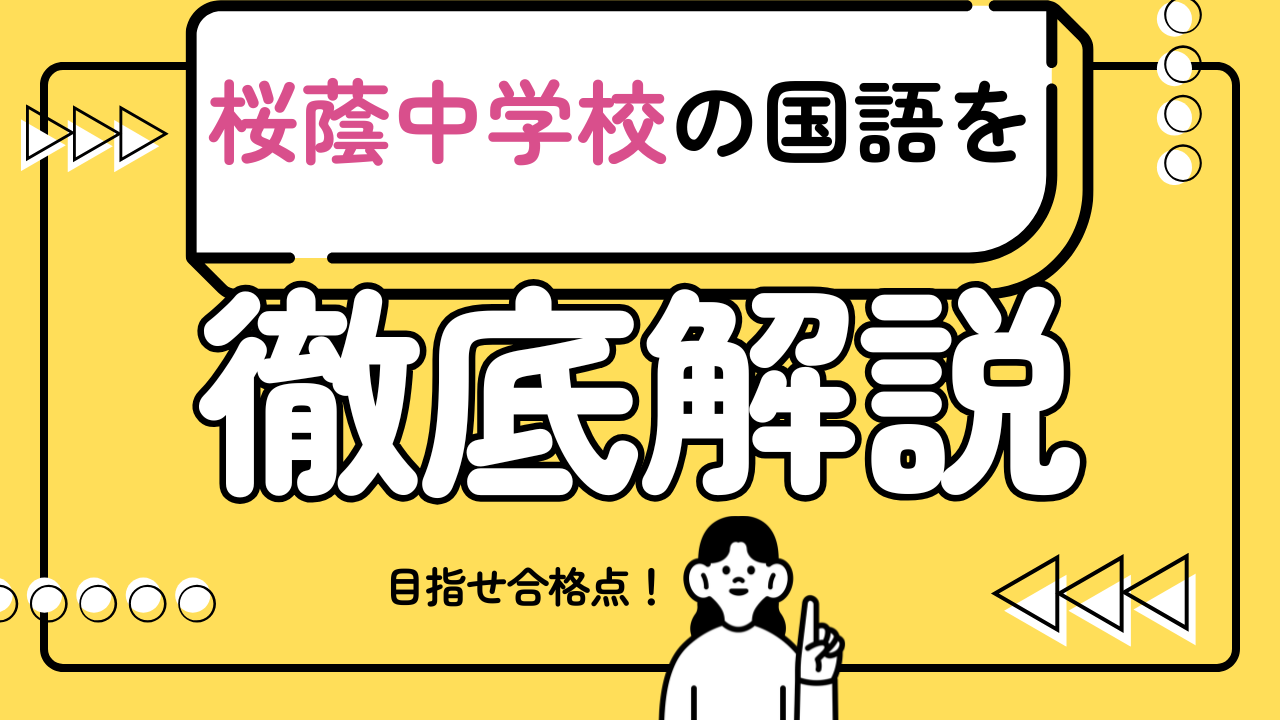- 東大生による国語専門個別指導 ヨミサマ。
- 記事一覧
- 【文武両道】週6部活×東大現役合格を成し遂げた齋藤先生の勉強法とは!?【講師インタビュー#07】

【文武両道】週6部活×東大現役合格を成し遂げた齋藤先生の勉強法とは!?【講師インタビュー#07】

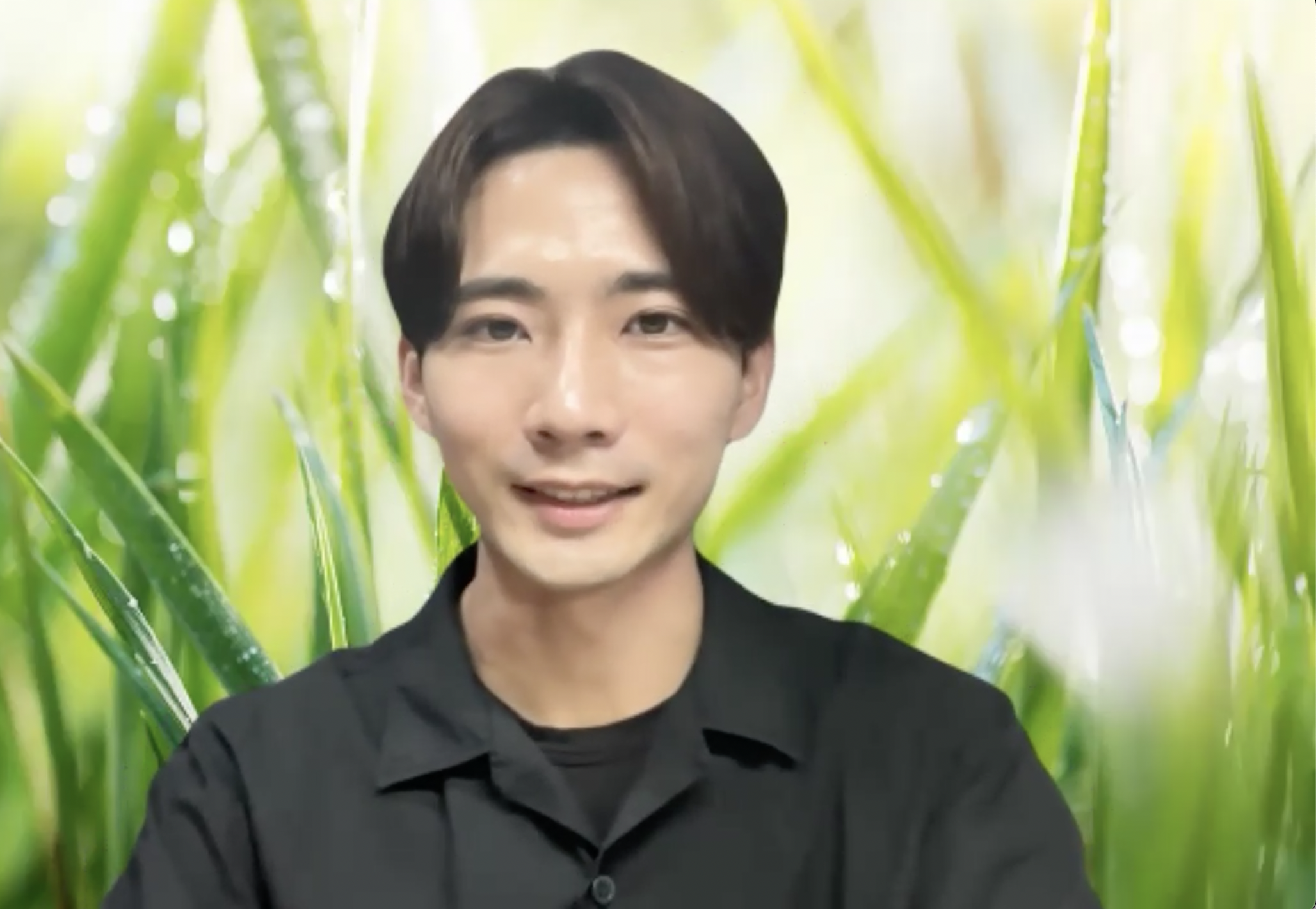
部活動に全力で打ち込みながらも、見事、東京大学文科一類への現役合格を果たした講師がいます。高校時代、週6日のバドミントン部に所属し、多忙な日々を送る中で、独自の学習法で難関大学受験を突破した齋藤慧先生です。
本記事では、そんな齋藤先生に、部活動と受験勉強の両立の秘訣、限られた時間で成果を出すための集中力の重要性、そして齋藤先生ならではのコミュニケーション力としての国語力について、そのリアルな経験を語っていただきます。
生徒目線で実践された、効率的かつ本質的な学習方法。その言葉の中には、これから受験を迎えるすべての中高生、そして保護者の皆様への貴重なヒントが詰まっていました。
部活漬けの高校生活から東大現役合格!
篠原鼓太(ヨミサマ。講師、兼運営。以下、篠原): こんにちは、篠原と申します。本日は貴重なお時間をいただき、ありがとうございます!
齋藤先生(ヨミサマ。講師。東京大学文科一類): こちらこそ、よろしくお願いいたします!ヨミサマ講師の齋藤慧です。
篠原: 齋藤先生は高校時代、週6日の部活動と難関大学受験を見事に両立させ、東京大学現役合格を掴んだと伺っています。その秘訣をぜひお聞かせいただきたいです。
齋藤先生: はい、承知いたしました。私の経験が少しでも皆さんの役に立てば嬉しいです。

篠原: まず、高校ではどのような部活動に所属されていたのでしょうか?また、その活動はどのくらいハードだったのでしょう?
齋藤先生: 長野県の県立高校でバドミントン部に所属していました 。活動は週6日、月曜日から金曜日は16時半から18時半まで2時間、土曜日は朝8時半から12時まで3時間半と、本当にみっちり活動していましたね 。家に帰ると、疲れてご飯を食べて、お風呂に入って寝る、というような毎日でした。
篠原: 週6日の部活動と、受験勉強の両立は想像を絶する大変さだと思います。しかも、部活動を引退するまでは塾にも通っていなかったと伺い、驚きました。
齋藤先生: はい、部活動を引退するまでは塾には一切通っていませんでした 。高校3年生の5月に引退した後、文化祭の準備期間を経て、本格的に塾に入ったのは7月の半ばからです 。周りの県立高校生も部活動引退が遅い中で、私も同様に遅れて受験勉強を始めた形です。
やらない日も肯定する独自の学習スタイル
篠原: そのような限られた時間の中で、どのように勉強と両立させていたのか、多くの小中高生が悩んでいると思います。齋藤先生ならではの時間の使い方や、勉強への優先順位について教えていただけますか?
齋藤先生: 一般的に考える両立って、1日の中に部活の時間と勉強の時間を設けるイメージだと思いますが、私は全くそうではなかったんです 。私の場合は、テスト前など部活がない期間に死ぬ気で勉強し、部活がある期間はほとんど勉強しないという生活を送っていました 。いわゆる1日の中で両方やるという両立はできていませんでしたね 。

篠原: なるほど!それは非常にユニークな発想ですね。オンオフの切り替えを日単位ではなく、週単位や期間単位で明確に分けていたということでしょうか?
齋藤先生: その通りです。部活がある日は部活のことしか考えない。部活がない期間は勉強のことしか考えない。そうやってスパンを区切ることで、それぞれの活動にものすごく集中できました 。私はコツコツ勉強するのが苦手なタイプだったので、勉強する日は「今日は勉強のことしか考えない」と決めて取り組んでいましたね 。この集中こそが、限られた時間で成果を出すための鍵だったと思います。
篠原: その集中力が、短時間でも効果的な学習に繋がったのですね。齋藤先生が特に意識していた勉強法はありますか?
齋藤先生: 短時間でも効果を出すためにずっと大事にしていたのは、何のためにこの勉強をしているのかという目的意識を明確に持つことです 。例えば、国語のワークを1ページ解くにしても、ただ解くのではなく、「今日はこういう読み方、解き方を試してみよう」とか、「それが自分に合っているか判断しよう」といった具体的な目的を持って取り組むんです 。
そうすることで、勉強の密度がものすごく高まります 。「今、自分は何をやっているんだろう?」という無駄な時間が限りなくゼロになるように意識していましたね 。これは、手段が目的化してしまうことを避ける意味でも非常に重要です。
⏬ヨミサマ。講師の現役東大生100人に聞いた、理想的な学習方法はこちら!!
復習ノートの活用
篠原: まさに「勉強のための勉強」にならないための工夫ですね。国語力といえば、継続して読んだり書いたりすることが重要だと感じますが、齋藤先生はどのようにその力を維持・向上させていましたか?
齋藤先生: 受験直前の話にはなってしまいますが、過去問や共通テスト、東大の過去問などを解く際に、何を考えながら解いたのか、結果はどうだったのか、次回どうしたいのかを全て教科ごとの復習ノートに日記のように記録していました 。
これを続けることで、以前自分が何を考えて勉強したのかを可視化でき、振り返ることができます 。一度やったことを忘れてしまって無駄になるのを防ぐ、つまり同じミスを繰り返さないための工夫でした 。私は勉強が嫌いなので、極限まで勉強時間を減らしたいという思いがあり(笑)、そのために密度の高い学習と、一度の学びを確実に次に繋げることを意識していましたね。
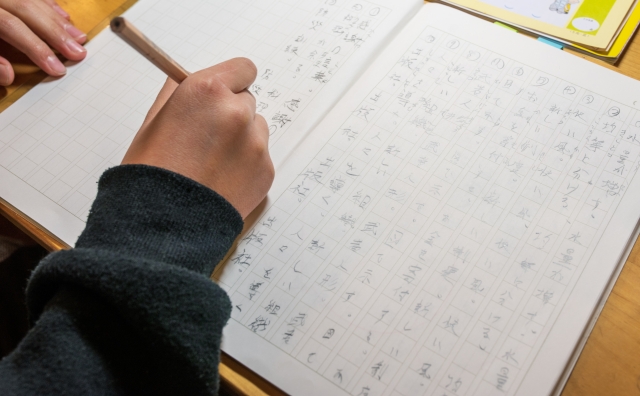
篠原: 自分の思考プロセスまで記録して、徹底的に効率を追求されていたのですね。モチベーションが上がらない時もあったと思いますが、どのように自分を奮い立たせていましたか?
齋藤先生: 正直、やる気が出ないときは勉強しませんでした 。一番良くないと思っているのが、勉強しないことで自己肯定感が下がってしまうことです 。やる気の波はあるので、やりたくない時はやりたくないんです 。だからこそ、やる気がある時に「俺はこれだけできるんだぞ」と、友人と競争したりして、精神的な勉強貯金をしておくんです 。 「今日はやる気が出ないけど、昨日これだけ頑張ったから大丈夫」と、やる気が出ない自分を肯定してあげる方に力を使っていました 。無理に奮い立たせるのではなく、やる気が出ない自分を肯定する。長期戦である受験において、メンタル管理も非常に重要だと考えていましたね 。
国語力とはコミュニケーション力
篠原: 齋藤先生の国語力に関する考え方も非常にユニークだと伺っています。齋藤先生にとって国語力とは一言でいうと何でしょうか?
齋藤先生: 私にとって国語力とは、ズバリ「コミュニケーション力」です 。

篠原: コミュニケーション力、ですか。その真意をぜひ教えてください。
齋藤先生: これは今まで話してきたことに集約されるのですが、一つは想像力です 。テストで言えば、問題を作った人が何を伝えたいのか、何を求めているのかを想像し、それに応える解答をすること 。これは紙面を使った採点者とのコミュニケーションだと考えています 。他の科目でも、日常生活でも、文字や言葉で伝えられ、それに対して何かを返す作業は全てコミュニケーションです 。
また、難しい文章に出会った時でも、「この筆者は、こう書くことが人に伝えるのに一番良いと信じて書いているんだ」と、書いた人への信頼を持って読むことも大切にしています 。その信頼があって初めて、筆者と自分の間で双方向のコミュニケーションが成立するんです 。ただ受け取るだけでなく、能動的に読み解き、時には「自分ならこうするのにな」といった想像とのズレを楽しむことが、国語にはまるきっかけになったりもします 。例えば、小説を読んでいて「こう話が進むんだろうな」と思ったら違ったという面白さに気づくこと 。これは能動的に文章と対話する感覚ですね 。
篠原: 想像力と信頼に基づく双方向のコミュニケーション。それはまさにヨミサマの個別指導で大切にしている対話そのものですね!
齋藤先生: そうですね。高校の授業が退屈に感じた時も、先生の板書をただ写すのではなく、「自分だったらこうまとめるのにな」と考えながら、あえて先生とは違うノートを取っていました 。これも、与えられた情報をただ受動的に受け取るのではなく、主体的に学習するための、自分なりのコミュニケーションだったのかもしれません。
⏬コミュニケーション力をつけるには、親子の対話も重要です。子供の国語力を伸ばすために、東大生の親が実践していたことを紹介します!
後輩たちへ:互いを言い訳にするな
篠原: 最後に、これから部活と勉強の両立に挑む後輩たちへ、齋藤先生からのメッセージをお願いします。
齋藤先生: 「互いを互いの言い訳にするな」と伝えたいです 。勉強が大変だから部活がおろそかになるのも駄目だし、部活が大変だから勉強がおろそかになるのも駄目 。どう時間を使うかは人それぞれですが、やる時はその活動に集中する。部活の時は部活に全力を注ぎ、勉強の時は勉強に全力を注ぐという、メリハリが何よりも重要です 。どちらも中途半端になるのではなく、一つひとつに集中する姿勢を持ってほしいですね。その中で、ヨミサマ。のような目的意識を持った学習をサポートしてくれる存在は、きっと大きな力になるはずです。
インタビュアー: 齋藤先生、本日は本当にありがとうございました!先生のメリハリのある学習法と、国語の本質を捉えた深いお話は、きっと多くの生徒さんの力になると思います。
編集後記
週6日の部活動と東大現役合格を見事に両立した齋藤先生のインタビュー、いかがでしたでしょうか。
齋藤先生のユニークな学習法は、オンとオフの切り替えにありました。部活がある日は部活に、ない日は勉強に、と徹底的に集中。このメリハリが、限られた時間で成果を出す鍵だったといいます。
さらに、何のために学ぶかという目的意識の明確化や、復習ノートで思考プロセスを可視化する工夫も、効率的な学習に繋がっています。
国語力=コミュニケーション力という考え方も印象的でした。問題作成者の意図を想像し、文章と対話する姿勢は、学力だけでなく人間力を高める示唆に富んでいます。
「互いを互いの言い訳にするな」という後輩へのメッセージは、部活も勉強も全力で取り組みたい学生たちへの力強いエールとなるでしょう。齋藤先生、貴重なお話をありがとうございました!
無料体験授業実施中!

国語力を劇的に変える60分
ヨミサマ。体験授業
- 自分の今の「国語力」が分かる!
- 大学生の国語の「解き方」を追体験!
- 成績の伸ばし方の見通しが立つ!
無料
公式LINEからカンタン30秒
体験授業を予約する
関連する他の記事もご覧ください!
この記事を編集した人
東大生がつくる国語特化の個別指導塾ヨミサマ。編集部です。国語のプロフェッショナルとして、国語が苦手な生徒から東大受験対策まで述べ二千人以上を指導してきた経験を記事にしてお伝えします。完全独学で東京大学文科Ⅰ類に合格し、「成績アップは国語で決まる!」著者の神田直樹が監修しています。
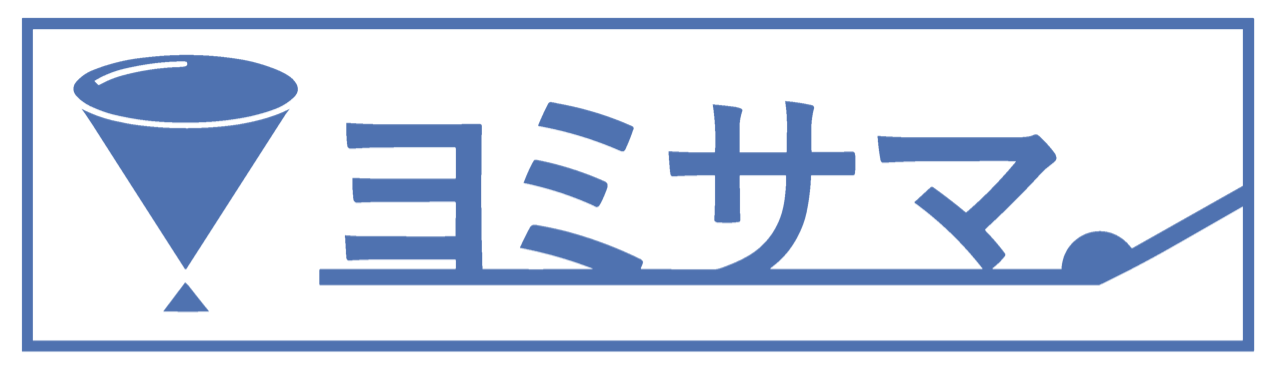
 【東大生の国語勉強法】国語の点数を上げる3つのシンプルなルール
【東大生の国語勉強法】国語の点数を上げる3つのシンプルなルール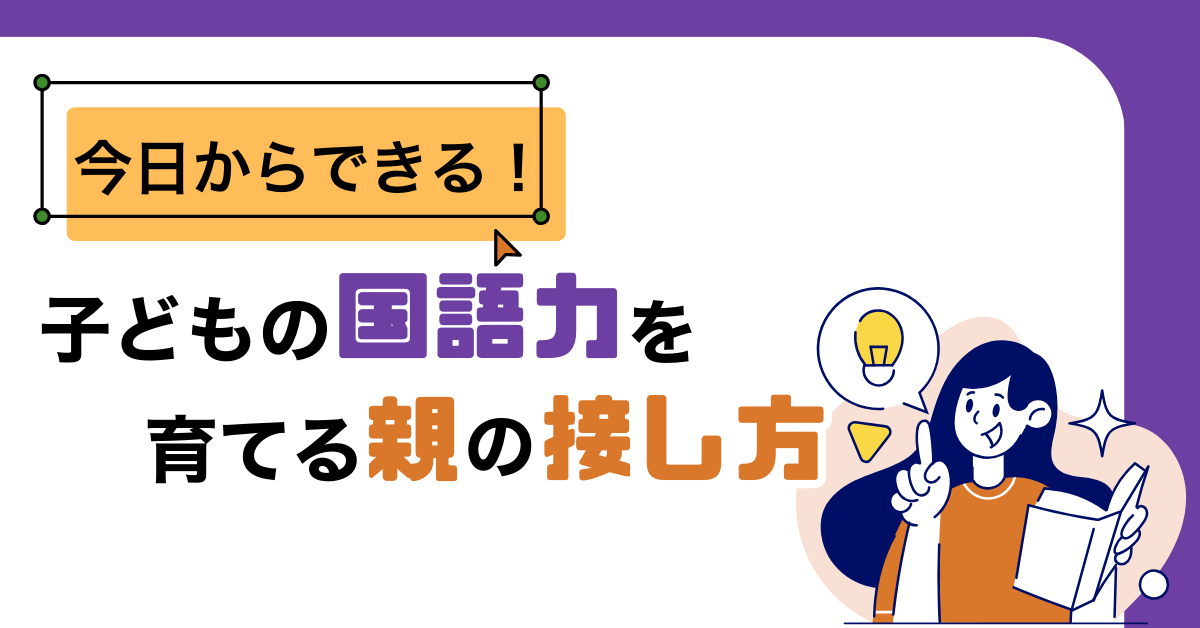 子どもの国語力を育てる接し方とは?【塾なし東大生の体験談】
子どもの国語力を育てる接し方とは?【塾なし東大生の体験談】
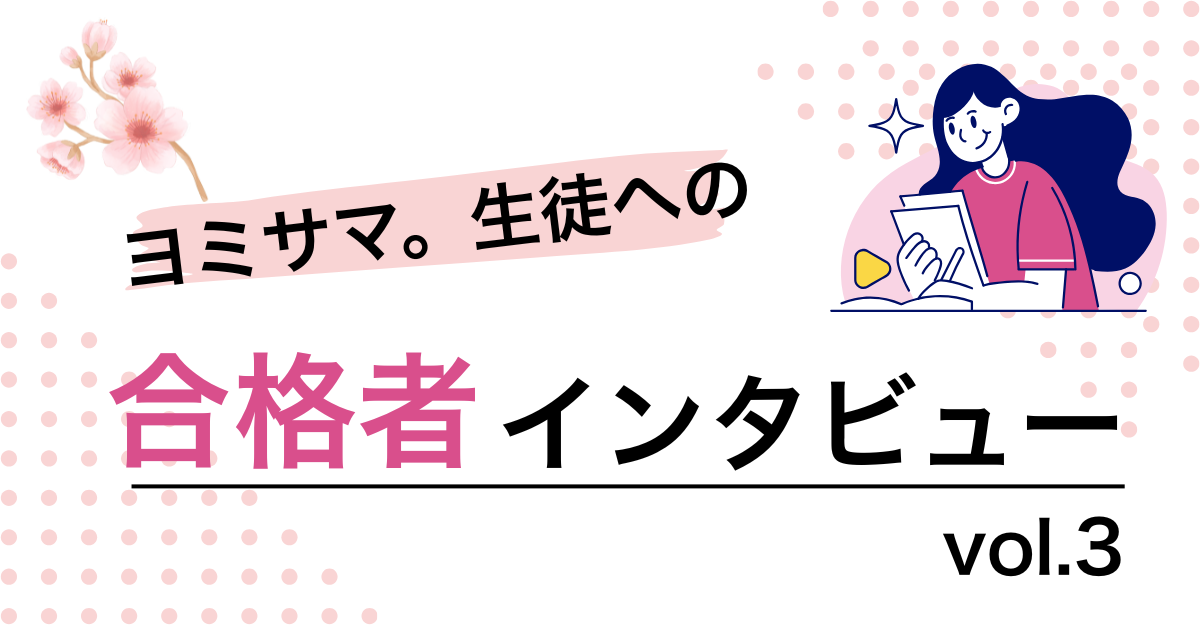 帰国子女で難関高校合格!合格を掴んだ国語の勉強法を初公開!【体験記#07】
帰国子女で難関高校合格!合格を掴んだ国語の勉強法を初公開!【体験記#07】