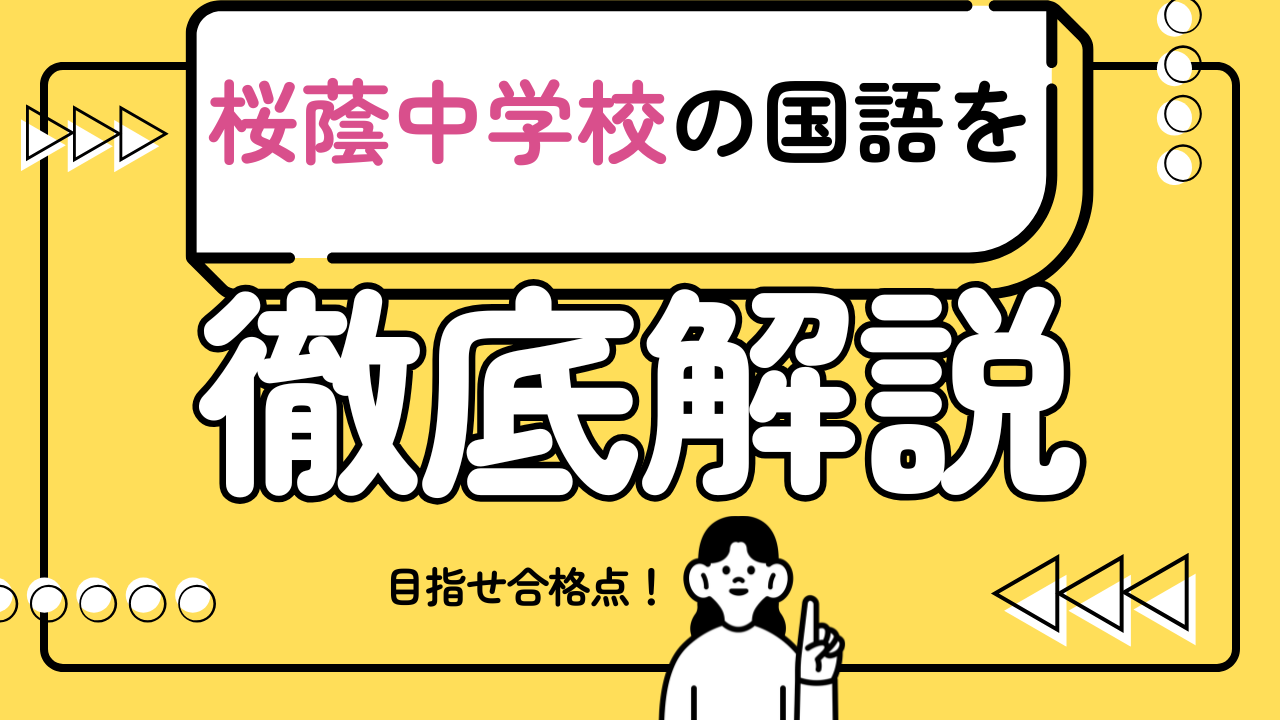- 東大生による国語専門個別指導 ヨミサマ。
- 記事一覧
- 子どもの国語力を育てる接し方とは?【塾なし東大生の体験談】
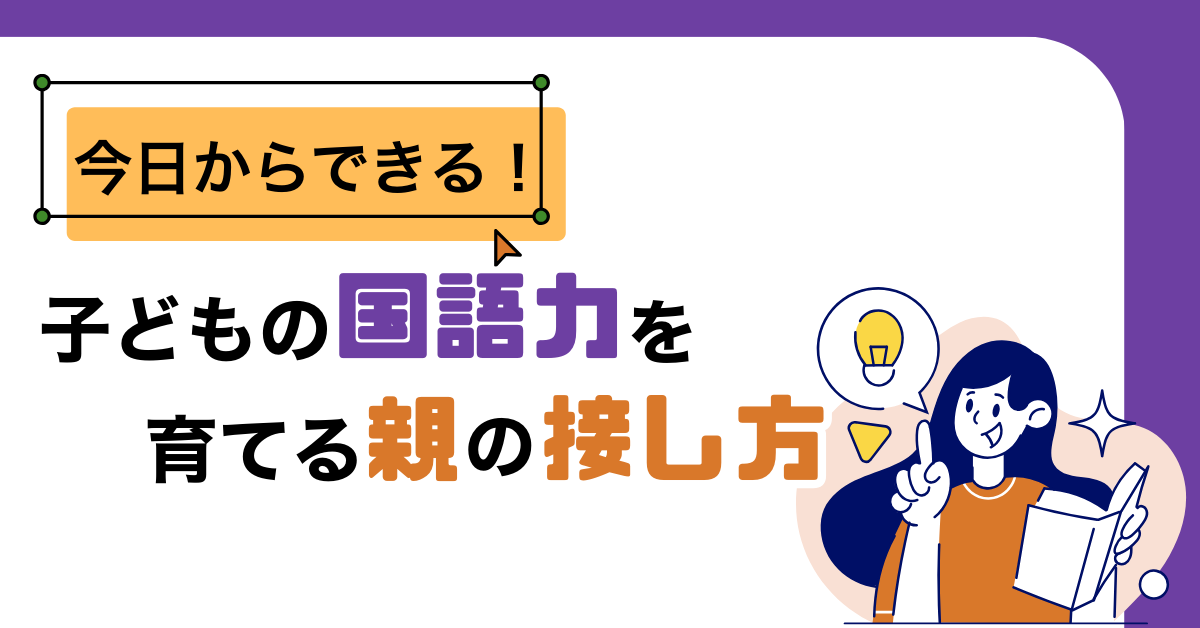
子どもの国語力を育てる接し方とは?【塾なし東大生の体験談】
こんにちは!ヨミサマ。編集部です!
東大生を中心に国語に特化した個別指導を行っている「ヨミサマ。」
今回は、ヨミサマ。の代表である神田と北によるトークセッションの内容から、親の接し方にフォーカスを当ててご紹介します!
まずは、二人の簡単なプロフィールから!
神田:
茨城生まれ東京育ち。中学1年生のときにドイツのミュンヘンに引っ越し、高校に通わずに独学で東京大学法学部に入学。
昨年マッキンゼーを退社し、「ヨミサマ。」を設立。
神田の記事はこちら
北:
公立中学校、県立浦和高校を経て、東京大学文科二類に主席合格。
高校時代は週6の部活、文化祭のリーダー、留学など、勉強だけに偏らず色々な体験をして過ごす。
すごい経歴ですね。
ところで、二人の共通点に気付くでしょうか?
そう、塾に通っていないんです!
東大に入るだけでも難しい上にそれを独学でやり遂げるのはとても難易度の高い事です。
では、なぜ二人はそれを成し遂げることができたのでしょうか。
その秘訣は国語力にあります。自力で学習を進めていくためには、参考書に書いてある文章を正しく理解する読解力が必要不可欠です。実際、二人とも「塾なしで東大に受かるには国語力が大事」と話していました。
実際、ほかの科目も授業や教科書はすべて日本語ですよね?そう、国語はすべての科目の土台となる教科です。そして、国語力が不足していれば当然ほかの科目もぐらついてきます。
そんな重要な国語ですが、私たちは生まれてからずっと国語をしているようなものです。言い換えれば、暗記科目のように短期間で伸ばすのはすごく難しく、幼少期の影響を最も受けるのが国語なんです。
そうだとすれば、二人が塾なしで東大合格をつかみ取った秘訣は、彼らの幼少期を過ごした環境にあるのではないでしょうか?
というわけで、今回のテーマは…
塾なし東大生の体験談、国語力を伸ばす親の接し方!!!
前置きが長くてウズウズしているかもしれません。
お待たせしました!
それでは本題に入っていきます!
国語力を伸ばす方法を東大生が本気で考えた!
対話により国語力を向上させる独自メゾットのオンライン個別指導ヨミサマ。!
HPはこちら!
とにかく活字に触れる
「頭のいい人は本を読んでいる。」
これは結構広く受け入れられたイメージではないでしょうか。
一方で、
「子どもがまったく本に興味を持ってくれない。」
これもあるあるだと思います。
この悩みの根底には、活字が生活に馴染んでいないことが挙げられます。生活サイクルの中に活字が含まれていないとなかなか習慣化できません。
そこで大事なのが活字を身近な存在にすること。
実際、神田と北の家でも活字が身近な存在だったそう。神田の場合、親も本が大好きで壁一面が本棚だったそう。(ちなみに、神田は活字中毒で、パッケージの裏の食品表示を全部読むらしいですよ。)
でも、活字を身近にって具体的にどうするのか?
「読ませようとしても読んでくれないよ!」
そう思う方もいるかもしれません。
大事なのは、活字を「読ませる」のではなく、活字が近くに「ある」状態を作ってあげること。例えば、食卓の上に新聞が置かれている。暇なときに手元に本がある。こういった状況を整えてあげることが重要なのです。
しっかりと「読もう!」と思うと腰が重いけれども、ふと目に止まった文字を読むのは意外と気軽にできます。そのうち、無意識に生活のサイクルの中に活字が入り込んできます。そうやって活字へのハードルを下げておくと、その先のステップへ進みやすくなります。
なので、活字を全く読まない子どもの場合はゲームの攻略本等でもいいので、好きな分野から読み始めるのもオススメです。
もちろん、これは入り口の話ではあります。でも、「知りたい」という欲求は根源的なものなので、情報を仕入れる手段として一度でも活字を定着させてしまえば自然と文章を読むようになります。そうやって、徐々に文章のレベルを上げていけるような環境を作ってあげると効果的です。
ところで、なぜ活字が大事なのでしょうか。
一言で言えば、文章を読む速度を上げることができるからです。
読む速度と言っても二種類あって、文章を目で追う速さと、読んでから理解するまでの速さがあります。そして、そのどちらもが活字を読んだ量に依存してきます。だからたくさん活字を読むことが大切なのです。
そして、文章を読む速度が上がるメリットは国語だけにとどまりません。
例えば歴史の勉強においても、教科書をサッと読んだだけで、誰が何をしたのか理解できれば周りと差を作れますよね。かなり極端な話ではあるんですが、単純化して考えると、読む速度が二倍なら高校三年間の勉強で六年分の効果を得られるわけです。これは、私個人の見解ですが、世に言う地頭とか吸収力ってここに繋がってくるんじゃないかと思っています。
とにかく、活字を身近な存在にすることでハードルが下がること、活字を読むことで国語以外の科目も良い影響があること、この二つをぜひ試してみてください!
子どもに話させる
皆さんのご家庭での会話はどんな感じでしょうか。
兄弟での会話が多い、父と子で一緒に遊んでいる、母がいちばんおしゃべり、などなど。
もちろん様々なパターンがあると思います。
ちなみに神田の家では、父:母:神田の話す割合が8:8:8だったそうです(笑)。全員が全員好きなことをしゃべって、聞かれていなくても気にしなかったとか。神田がすらすらと論理的な話ができるのはこれに起因しているのかもしれないですね。
話を戻すと、子ども時代の家庭での会話は学力だけに限らずその後の人生に大きな影響を与えます。まずはその中でも親と子の会話に目を向けていきましょう。
子どもとの対話は国語力を鍛えるうえで非常に重要になってきます。
これはヨミサマ。の本質にも関わってくるのですが、「話す」という事は非常に国語力を鍛える上で効果を発揮します。インプットされた情報を頭の中で整理し、自分の意見を相手に論理的に伝える。もはや、媒体が筆記なのか声なのかが異なるだけで実質国語ですよね。
親子の対話で理想的なのは、子どもと親の話す量が1:1になっている事です。
しかし、実際にはなかなか難しい事ですよね。
特に多いのが、「子どもの話す内容が支離滅裂である」や「あまり話してくれず親ばかり喋ってしまう」といったことではないでしょうか。
そこで、子どもにうまく話してもらうコツをお伝えします!
話す量を1:1にするために重要な事は、親が先行して話すことです。親が先に話して、話の基準となる軸を作ることで子どもはとても話しやすくなります。
「生みの苦しみ」という言葉があるように、人間はゼロから何かを生み出すのはとても労力を使います。それに対して、既にあるものに対して意見を言うことはグッとハードルが下がります。そこで親が先行して着火剤の役割を担うことで子供の意見を引き出す事ができます。
「〇〇についてどう思う?」
このように子供に親側から積極的にテーマを設定する方法をぜひ試してみてください。
それから、ひとつ注意しなければいけないのは子どもの意見を頭ごなしに否定しない事です。どれだけ突拍子のない発言だったとしても、子どもの中ではその考えに至った経緯が必ずあるはずです。なので、なぜそう考えたのか、1ステップずつ紐ほどいてあげることで子どものやる気をそぐことなく対話を深めることができます。
手本を見せる
対話つながりで言えば、この親にしてこの子ありという言葉がある通り、親が手本を見せることも当然のことながら重要となってきます。
本や新聞を日常的に読んでいたり、親同士で難しそうな経済の話をしていたり。
様々な手本の見せ方があると思うのですが、今回は大人同士の会話に着目してみましょう。
ひとつ前の段落でお伝えした通り、対話によって自分の考えをアウトプットさせることは非常に効果があります。ですが、インプットがなければアウトプットの意味も薄れてしまいます。
例えば、スポーツであればプロの試合を見ますよね?自分がやっているスポーツのプロは直接であれ動画であれ一回くらい見たことがあるのではないでしょうか。目指すところがはっきりとわかっている事で一気に練習の質を上げることができます。
ですが、勉強になると高度なお手本というのが少なくなってしまいます。もちろん教科書や学校の先生はお手本の一つなのですが、それらはすべて子供に向けられた言葉達です。
人々が子どもに向けて発する言葉は、少なからず分かりやすく整えられ、ラッピングされています。もちろん優しさゆえなのですが、そのような中で高度な日本語に接する機会を確保するのは実は難しい事です。
そこで重要なのが大人同士の対話です。子どもにとって一番身近なインプット対象は他でもない親です。子どもに向けられた優しい言葉ではなく、大人同士が自分の意見を相手に納得させるためにどのように論理を組み立てているのか。大人同士だからこそ出せる手加減のない高度な日本語を見せることが大切です。
ですから、ぜひ子供の前で最近話題のニュースなどについて討論してみてください。
では、親の国語力が高くないと子どもの国語力は育たないのでしょうか。
「ディベートなんてそんな難しいことはできない」
「そんなにまとまった時間をとるのは難しい」
このような方々も一定数いると思います。
ご安心ください。普段から目の前で接するのには及ばないですが、代替手段はあります。
その一つが討論番組です。現代ではデジタルコンテンツが発達し、高い国語力を持つ方々の討論を簡単に見ることができます。コンテンツ選びは難しいところですが、高校生のディベート大会など少し上くらいの年齢なんかを見せるのも具体的な目標ができていいのではないかと思います。

勉強しろと言わない
勉強の悩みで大きな部分を占めるのは、そもそも勉強をやろうとしない事ではないでしょうか。では、勉強の意欲を持続させるためにはどうすればいいのでしょうか。
子どもも勉強をするべきなのはわかっています。やろうという気持ちから行動に移す、このステップが実はとても難しいんです。
一方で、人のやる気というのは行動し始めてからじゃないと出ないという研究もあります。親としては、勉強を始める回数を少しでも増やしてあげたいですよね。
では、どのようにして子どもに勉強を始めさせるのか。
一つ、重要なのは環境づくりです。図書館や自習室に行くなど、「自分も勉強しなければ」と思えるような場所に身を置くのは効果的です。家で勉強する場合であれば、保護者も一緒に何かを頑張っている状態を作ることが望ましいです。極端な話、親がテレビやスマホを見ているのに子どもだけ勉強しなさいって言われても、そんなの無茶な話です。ですから、家計簿をつける、資格の勉強をする、家事をするなど、親側も頑張るから一緒に頑張ろうというスタンスを大切にしましょう。
また、子どもに勉強しなさいと言うのは、あまり効果的ではありません。もちろん勉強することで視野が広がったり、将来の選択肢が増えるなどメリットはたくさんあります。しかし、子どものうちはそれらを言葉で表面的に理解していてもどうもピンと来ていないものです。大人からしたら子どもの成長は早いですが、子どもから見ると大人なんて遥かに遠い未来の話です。
なので、勉強を強制したり、勉強の利点を説くことはあまり効果的ではありません。その代わりに、分からなかったことが分かるようになる、その楽しさを大切にしましょう。勉強の好き嫌いに関わらず誰でも、秘密にされれば知りたくなりますよね?このように知的好奇心は人間の根本的な感情の一つです。なので、分かることの楽しさを知った子ならば自然と勉強するようになります。
勉強をしやすい環境を作って、楽しく勉強すること。これが、勉強が長続きする秘訣です。

最後に
いかがだったでしょうか?
勉強の悩みは一人一人違うので難しい所ではありますが、ぜひお子様と向き合う際に今回の内容を参考にしてみてください。
また、今回の内容をすべて親御様で抱え込む必要もございません。
ヨミサマ。は対話を通じてひとりひとりと向き合い、国語力を上げる手助けをしています。ぜひ一度、無料の初回体験へお越しください!
国語力の変化を体感する60分
無料
公式LINEからカンタン30秒
体験授業を予約する
関連する他の記事もご覧ください!
この記事を編集した人
東大生がつくる国語特化の個別指導塾ヨミサマ。編集部です。国語のプロフェッショナルとして、国語が苦手な生徒から東大受験対策まで述べ二千人以上を指導してきた経験を記事にしてお伝えします。完全独学で東京大学文科Ⅰ類に合格し、「成績アップは国語で決まる!」著者の神田直樹が監修しています。
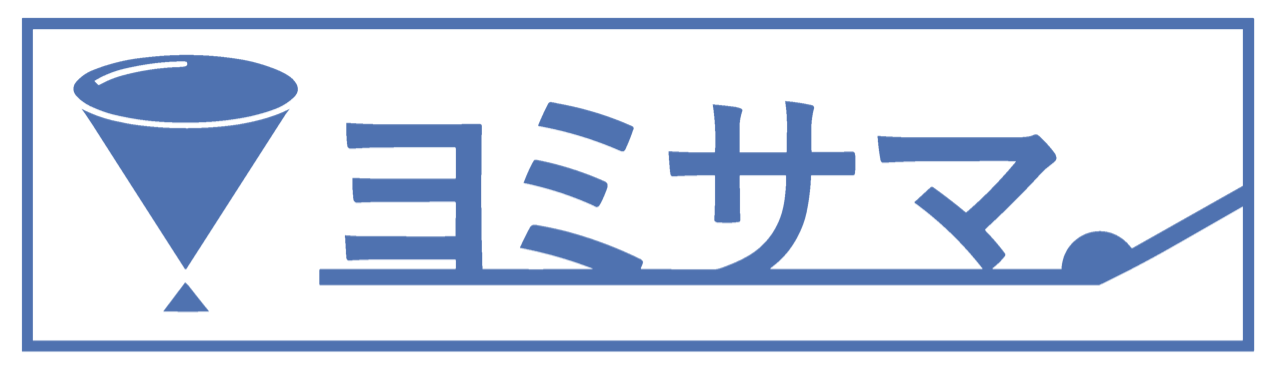
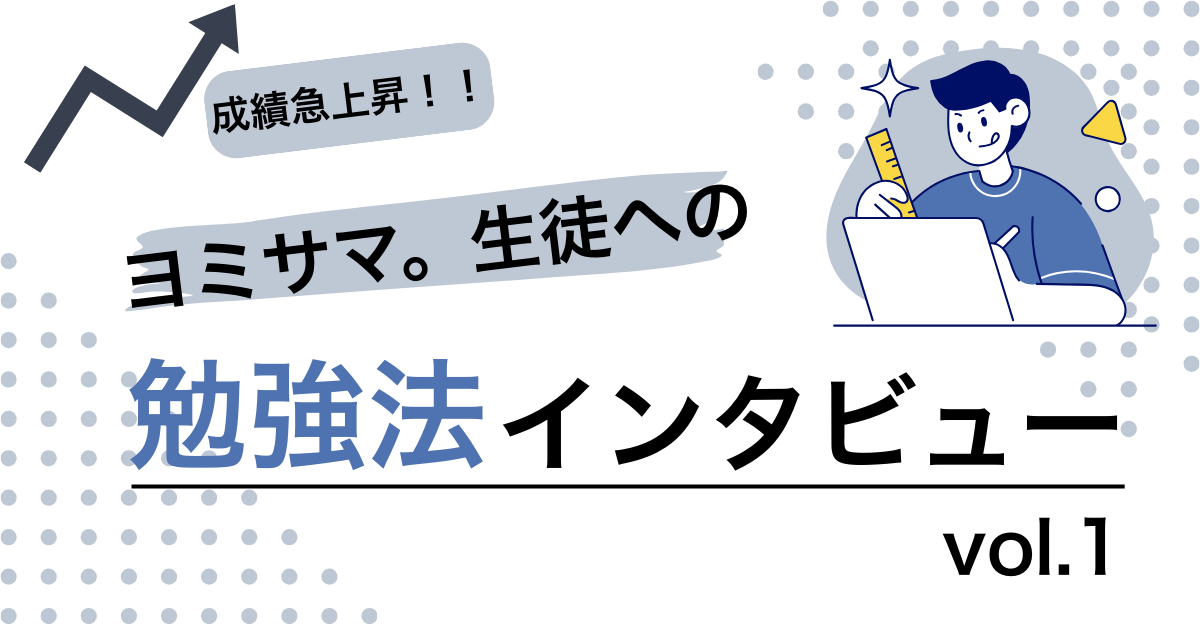 国語力向上の秘訣!「ヨミサマ。」で成績が大幅アップした高校生のインタビュー
国語力向上の秘訣!「ヨミサマ。」で成績が大幅アップした高校生のインタビュー  国語の勉強法で最も効果があったもの【東大生100人に訊いた】
国語の勉強法で最も効果があったもの【東大生100人に訊いた】