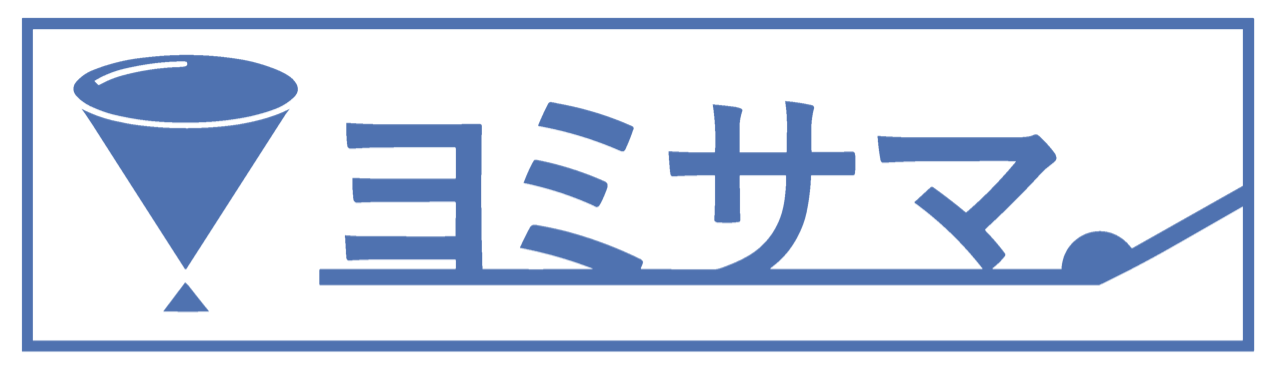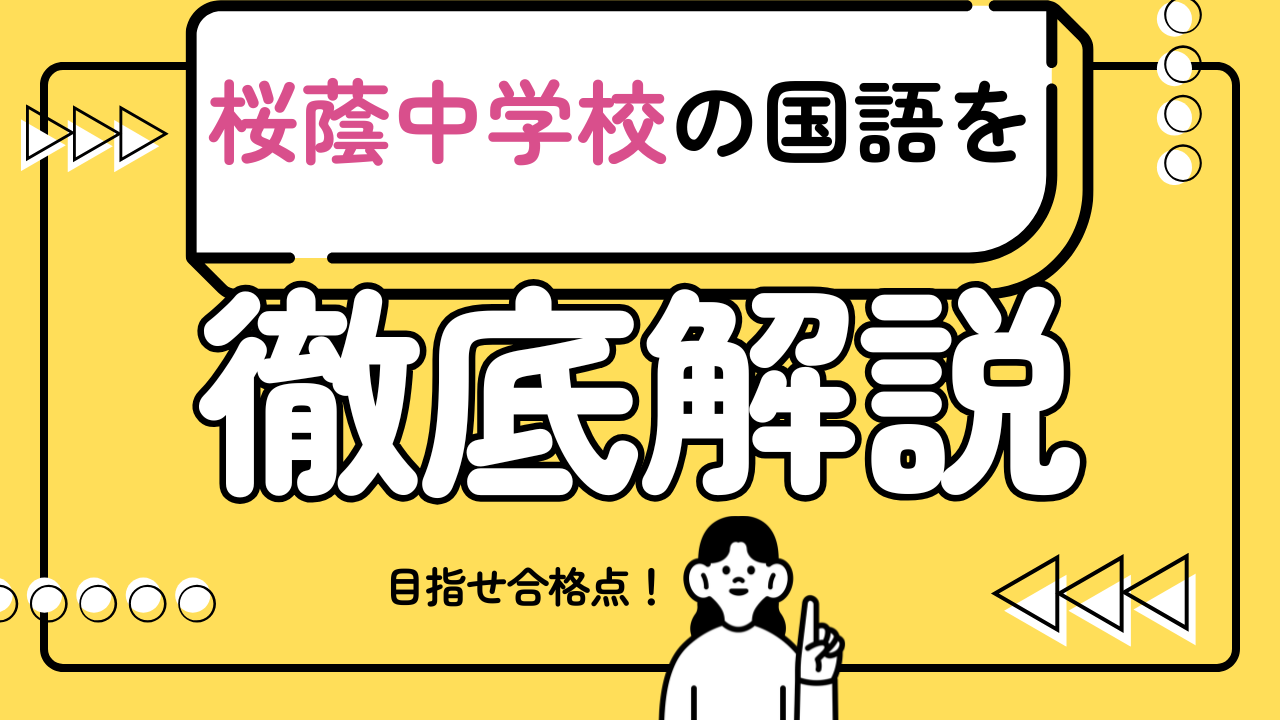- 東大生による国語専門個別指導 ヨミサマ。
- 記事一覧
- 小学生でもできる!論理的な話し方のコツ
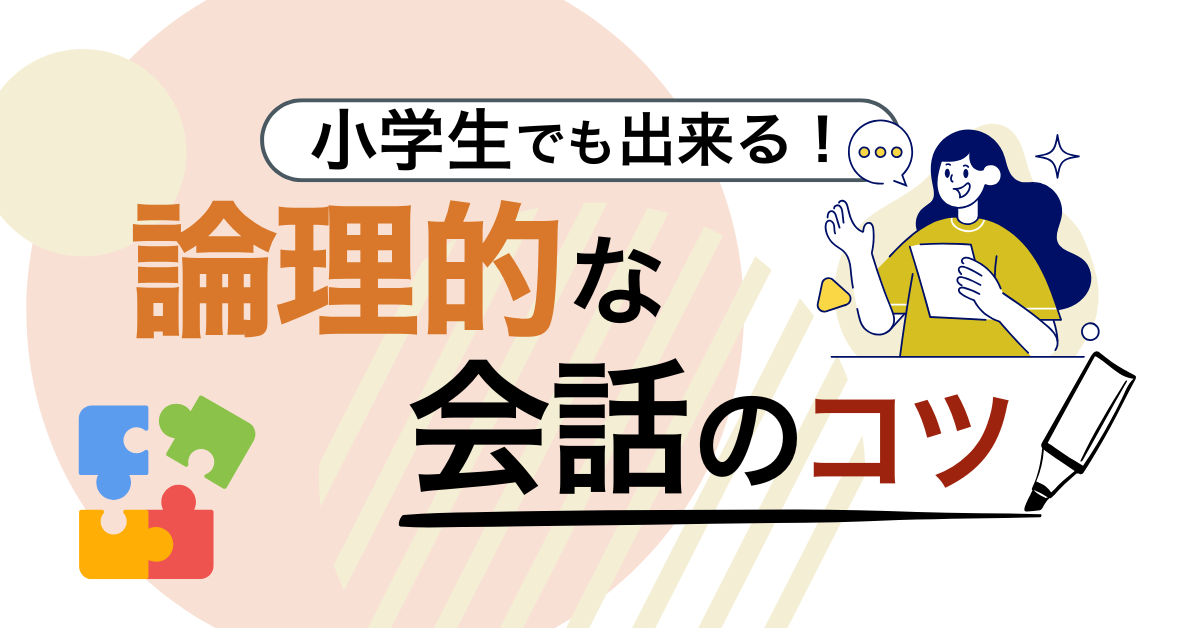
小学生でもできる!論理的な話し方のコツ
目次
はじめに
こんにちは! 国語特化の個別指導塾「ヨミサマ。」編集部です。
「話しているうちに、自分でも何を言いたいのかわからなくなってしまう」
「自分の意見をうまく伝えられない……」
そんな悩みを抱える小学生は、実はとても多いです。 私が講師をしている塾ヨミサマ。でも、「うまく話せないんです」と自分の話し方に自信を持てない生徒さんは多いです。
ですが、コツさえ掴めば、論理的に話すことは必ずできるようになります!
そこで、この記事では、小学生でもすぐに実践できる話し方のコツをわかりやすく紹介します。
この記事を読めば、学校の発表やディスカッションはもちろん、中学受験の面接でもきっと役立ちます!
論理的に話せるようになることに興味のある方はぜひ最後までお読み下さい。

小学生でもできる!論理的に話すための4つのコツ
- 立場と結論を明確にする
- 他の立場の人のことも考える
- グループ分けをして考える
- 原因をPUSH/PULLで分けて考える
① 立場・結論を明確にする
まず大事なのは、自分の立場や考えを最初に伝えることです。聞く人が一番知りたいのは、「この人は結局、どう思っているのか?」ということだからです。ですので、話すときには、最初に自分の立場(賛成か反対か)・結論を伝えましょう。
例えば、以下のような学校内の討論の一部について最初に自分の立場を言うとどうなるか見てみましょう。
「わたしは朝読書の時間を継続して設けるという木下さんの意見に賛成です。なぜなら、学校で本を読む時間をとることで、読書を好きになる可能性が高くなるからです。」
「ぼくは学校の宿題はあったほうがいいと思います。なぜなら、家で勉強するくせをつけることができるからです。」

このように、最初に「わたしは賛成です」「ぼくは○○だと思います」などと自分の立場を言い切るだけで、聞いている人は内容をずっと理解しやすくなります。
② いろんな立場の人のことも考えてみる
自分の考えだけでなく、反対の意見やちがう立場も考えることができると、説得力がぐんとアップします。ですので、自分の考えを話すときには、他の立場の人の考えを踏まえて自分の考えを伝えましょう。
そのためには、「自分はこう思うけれど、もし違う立場の人だったらどう思うだろう?」と想像することが必要です。
例えば、先程の討論についても以下のように反対の立場の意見も踏まえた発言が出来れば、より論理的な会話に近づくでしょう。
「わたしは朝読書に賛成です。でも、朝読書のために本を選んだり持ってきたりすることが面倒だという人もいると思います。ですが、朝読書をきっかけに好きな本ができたり読書を好きになったりするかもしれないので、本を選ぶのが面倒だと思う人にこそ、朝読書にはいい効果があると思います。」
「宿題がないと、友達と遊ぶ時間が増えてうれしいと思う人もいるかもしれません。でも、毎日少しずつ勉強することも大事だと思うので、ぼくは宿題があったほうがいいと思います。」
相手の意見もふまえて話すことができると、「なるほど」と思ってもらえる力が高まります。
③ グループ分けをして考える
よりわかりやすく話すためには、グループに分けて考えることもおすすめです。そしてその場合には、もれなく・ダブりなく(MECEに)グループ分けをすることが必要です。
MECEとは?
MECE(ミーシー)とは、「もれなく・ダブりなく」グループ分けをする考え方のことです。
- もれなく:必要なものが全部入っている
- ダブりなく:同じものがかぶっていない
この考え方でグループ分けをすると、話や考えがスッキリ整理され、分かりやすくなるというメリットがあります。
例えば、クラスをいくつかのグループに分ける場合を考えてみましょう。勿論、時と場合によって最適な分け方は異なります。しかし、以下のNG例を見てみましょう。
【NG例】
グループ1:運動が得意な子
グループ2:おしゃべりが好きな子
グループ3:勉強ができる子
これは一見よさそうに見えても、「もれ」や「ダブり」があります。 運動も得意じゃないし、おしゃべりもせず、勉強も苦手な子は、どこにも入れません。 また、運動もできておしゃべりも好きな子は、複数のグループに入ってしまいます。
この方法は、MECEに従っておらず、グループ分けとしては良くない例と言えます。
その一方で、以下のような分け方ならば「もれなく・ダブりなく」グループ分けが出来るので、よりよい方法と言えます。
【改善例】
- 出席番号ごとに10人ずつ分ける
- 性別(男子/女子)
- 学年別(1年生/2年生/3年生…)
このように、どの子もどこかに入り、かぶりがないような分け方をすることで、議論や話し合いがスムーズになります。
④ 原因をPUSH/PULLで分けて考える
「なぜそうなったのか?」という原因を考えるときには、一方向だけでなく、多角的に考えることが必要です。そこで役立つのが、PUSH要因とPULL要因という考え方です。
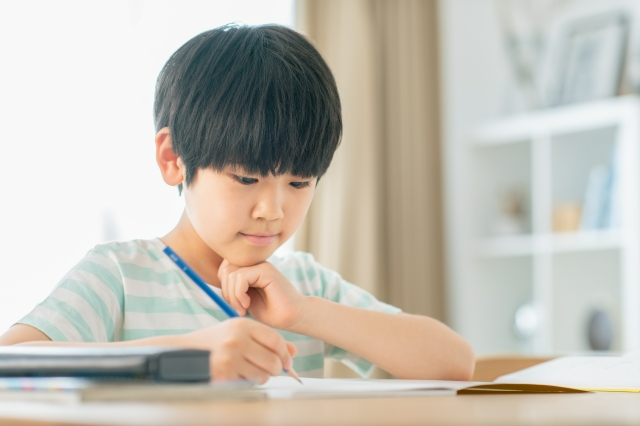
- PUSH要因:押し出される理由
- PULL要因:引きつけられる理由
例えば、スマートフォンの利用が増えた理由について考えてみましょう。
「スマホは便利だから」という1つの理由だけで説明してしまうと、一方向から(PULL要因)しか考えられていないことになります。
でも、多角的に見ると…
- PUSH要因:前のものが使いにくくなった
例)昔のガラケーではSNSや動画が使いづらかった。 - PULL要因:新しいものが魅力的だった
例) スマホではLINEもYouTubeもすぐ見られて、アプリもたくさんある。
このように、「古いものから押し出された理由(PUSH)」と「新しいものに引き寄せられた理由(PULL)」の両方をセットで考えることで、なぜ変化が起きたのかを正しく・深く理解できます。
家庭でできる!論理的思考を育てる工夫
さらに、論理的に話す力は、家庭でも育てることができます。保護者の方ができることを2つ紹介します。
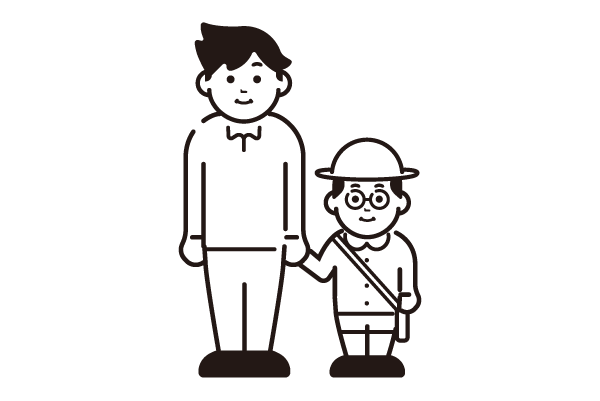
① 大人の会話を子どもに浴びせる
子ども向けの言葉だけでなく、大人の会話を日常の中で聞かせることが大切です。 例えば、「どうしてそう思ったの?」「なぜこっちを選んだの?」といった問いかけをすることで、子どもは考える習慣を自然と身につけていきます。
また、大人の会話の場に子どもを連れて行くのも有効です。
例えば、私の親は家でちょっとした食事会を開くことも多かったのですが、その場で大人の会話をたくさん聞いていたことが、今の語彙力の向上につながったと感じます。
② 親が「考えながら話す姿」を見せる
また、日常の中で「理由をつけて話す姿」を見せることも効果的です。 例えば、「今日はお肉の安売りの日だから、このスーパーに行こう」 というように、理由をつけて話すことが子どもの論理的思考のヒントになります。

まとめ
論理的な話し方は、特別な才能がなくても身につけることができます。
大事なのは、次の4つのステップです。
- 立場と結論をはっきり言う
- 他の立場の人のことも考える
- グループ分けで整理して話す
- 原因をPUSH/PULLで分けて考える
そして、親御さんの方からお子さんに働きかけるのもとても有効です。例えば、日々の会話を工夫して、お子さんが「なぜ?」「どうして?」を意識するようにすることができます。
論理的に思考することが習慣になれば、論理的に話せるようになるのもすぐです。話すことに苦手意識を感じているお子さんも、少しずつ自信を持てるようになりますよ!
そして、話す力を国語のプロと一対一で高められるのが「ヨミサマ。」です。まずは無料体験からお気軽に!
無料体験授業実施中!

国語力を劇的に変える60分
ヨミサマ。体験授業
- 自分の今の「国語力」が分かる!
- 大学生の国語の「解き方」を追体験!
- 成績の伸ばし方の見通しが立つ!
無料
公式LINEからカンタン30秒
体験授業を予約する
この記事を編集した人
東大生がつくる国語特化の個別指導塾ヨミサマ。編集部です。ヨミサマ。講師の東大受験や指導の経験をもとに、国語や受験にまつわるお役立ち情報を発信していきます!